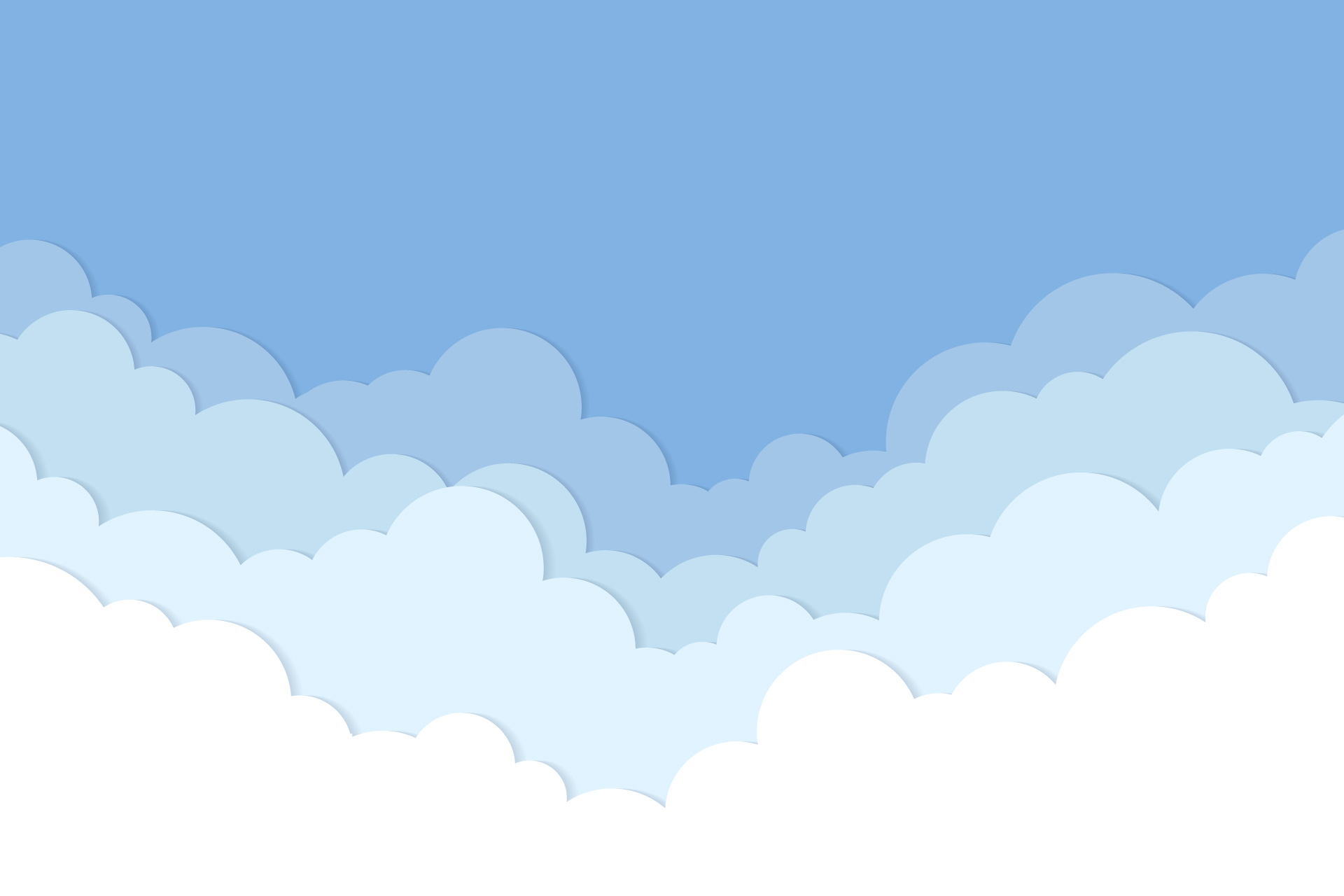交通事故で人身事故の被害に遭われた方にとって、慰謝料は精神的苦痛に対する重要な補償です。しかし、適正な慰謝料を獲得するには、相場や計算方法を理解し、保険会社との交渉を適切に進める必要があります。
本記事では、人身事故における慰謝料の種類、相場、計算方法から慰謝料が増額・減額するケースまで、被害者の方が知っておくべき情報を詳しく解説します。
人身事故における慰謝料とは
人身事故とは、交通事故により被害者がケガをしたり、死亡したりした事故を指します。例えば、追突されてむちうちになった、横断歩道で車にはねられ骨折した、などが該当します。
人身事故の被害者は、身体的な痛みだけでなく、治療の辛さや後遺症への不安など、大きな精神的苦痛を受けます。この精神的苦痛に対する金銭的補償が「慰謝料」です。
なお、慰謝料は人身事故の場合にのみ発生し、物損事故(物的損害のみの事故)では原則として認められません。物損事故では、破損した物の修理費や代替品の費用を賠償することで原状が回復されると考えられているためです。
2. 慰謝料の種類と内容
人身事故の被害者が請求できる慰謝料には、以下の3種類があります。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、事故によるケガで入院や通院を強いられたことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。入通院期間(初診日から治療終了日または症状固定日まで)や実際に入通院した日数をもとに算定されます。
入通院慰謝料の算定要素
- 入通院期間の長さ
- 実際の入通院日数
- 通院頻度
- ケガの症状や部位
- 治療内容(手術の有無など)
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺障害は、治療を続けても回復する見込みがなくなった「症状固定」の時点で残っている症状について、自賠責保険の後遺障害等級(1級~14級)の認定を受けることで請求できます。
後遺障害慰謝料の算定要素
- 認定された後遺障害等級
- 後遺障害の部位や内容
- 日常生活や仕事への影響
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、事故により被害者が死亡した場合の、本人および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料です。被害者本人の慰謝料は相続人が受け取り、また遺族固有の慰謝料も請求できます。
死亡慰謝料の算定要素
- 亡くなった被害者の年齢
- 家庭内での立場(一家の大黒柱か否か)
- 遺族の人数や構成
- 扶養関係の有無
3. 慰謝料の算定基準と相場
慰謝料の算定には3つの基準があり、どの基準で計算するかによって金額が大きく異なります。
自賠責基準
自動車賠償責任保険(自賠責保険)の支払基準で、最低限の補償を定めています。3つの基準の中で最も低額です。
自賠責基準の特徴
- 最低補償の基準
- 入通院慰謝料は1日4,300円で計算
- 傷害(入通院)に関する補償の上限は120万円
- 後遺障害等級ごとに定額(14級は32万円、1級は1,650万円)
- 死亡慰謝料は本人分が400万円、遺族分が550万円~950万円
任意保険基準
各保険会社が独自に設定する基準です。保険会社ごとに異なり、公表されていません。一般的に自賠責基準よりやや高めですが、弁護士基準より低い金額になります。
任意保険基準の特徴
- 保険会社ごとに異なる非公開の基準
- 自賠責基準より若干高い程度
- 保険会社の利益を考慮した基準のため、被害者にとって十分な補償とは言えない
弁護士基準(裁判基準)
過去の裁判例をもとに作られた「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤本」)に基づく基準です。3つの基準の中で最も高額となり、裁判でもこの基準が使われます。
弁護士基準の特徴
- 3つの基準の中で最も高額
- むち打ち症で他覚所見が無い場合(自覚症状のみの場合)や軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合と、そうでない場合とで別の計算表を使用
- 入通院慰謝料は入院・通院期間に応じて決定(例:むちうちで6ヶ月通院なら89万円、重症で6ヶ月通院なら116万円)
- 後遺障害慰謝料は等級に応じて110万円~2,800万円
- 死亡慰謝料は立場に応じて2,000万円~2,800万円
各基準の慰謝料相場の比較
入通院慰謝料の相場比較(むちうちで6ヶ月通院、実通院日数60日の場合)
- 自賠責基準:51万6,000円(4,300円×60日×2)
- 任意保険基準:約60万円~70万円
- 弁護士基準:89万円
後遺障害慰謝料の相場比較(14級の場合)
- 自賠責基準:32万円
- 任意保険基準:約40万円
- 弁護士基準:110万円
死亡慰謝料の相場比較(一家の大黒柱の場合)
- 自賠責基準:1,350万円(本人400万円+遺族750万円+扶養加算200万円)
- 任意保険基準:約1,500万円~2,000万円
- 弁護士基準:2,800万円
4. 人身事故の慰謝料計算方法
各種慰謝料の具体的な計算方法を見ていきましょう。
入通院慰謝料の計算
自賠責基準の計算式
自賠責基準では、以下の2つの計算結果を比較し、少ない方を採用します。
- 4,300円×入通院期間の日数
- 4,300円×実際に通院した日数×2
例えば、通院期間が180日、実際の通院日数が60日の場合:
- 4,300円×180日=77万4,000円
- 4,300円×60日×2=51万6,000円
この場合、51万6,000円が入通院慰謝料となります。
弁護士基準の計算式
弁護士基準では、ケガの種類と入通院期間から専用の表を使って算出します。
- 骨折、脱臼、他覚所見のあるむちうちなど重症のケガ→「別表Ⅰ」
- 軽いすり傷や打撲、他覚所見のないむちうちなど軽症のケガ→「別表Ⅱ」
例えば、他覚所見のないむちうち、入院なし、通院6ヶ月の場合、別表Ⅱを使うと89万円となります。
後遺障害慰謝料の計算
後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて金額が決まります。
自賠責基準の場合
- 14級:32万円
- 12級:94万円
- 9級:249万円
- 7級:419万円
- 5級:618万円
- 3級:861万円
- 1級:1,150万円(介護を要する場合は1,650万円)
弁護士基準の場合
- 14級:110万円
- 12級:290万円
- 9級:690万円
- 7級:1,000万円
- 5級:1,400万円
- 3級:1,990万円
- 1級:2,800万円
死亡慰謝料の計算
自賠責基準の場合
- 本人への死亡慰謝料:400万円
- 遺族への慰謝料:
- 遺族1人:550万円
- 遺族2人:650万円
- 遺族3人以上:750万円
- 被害者に扶養家族がいる場合:200万円を加算
例えば、夫婦と子4人の6人家族で、一家の大黒柱である夫が死亡した場合: 400万円+750万円+200万円=1,350万円
弁護士基準の場合
被害者の家庭内での立場により金額が異なります。
- 一家の支柱:2,800万円
- 配偶者・母親:2,500万円
- その他(子供・高齢者など):2,000万円~2,500万円
5. 慰謝料が増額・減額するケース
基本的な相場に加えて、以下のような事情がある場合、慰謝料が増減することがあります。
慰謝料が増額するケース
- 事故態様が悪質な場合
- 飲酒運転、無免許運転、著しい速度超過、ひき逃げなど
- 加害者の態度が悪質な場合
- 救護義務を怠ったなど
- 被害者の精神的苦痛が特に大きい場合
- 事故により失業した、治療が過酷だった、家族を失い精神疾患になったなど
- 後遺症が特に重い影響を与える場合
- 顔面に醜状痕が残った、若い女性の場合など
慰謝料が減額するケース
- 素因減額(既往症の影響)
- 事故前からの持病が治療の長期化や後遺障害の原因となった場合
- 通院日数が極端に少ない場合
- 通院期間が長いのに実際の通院回数が少ない場合
- 過失相殺(被害者にも過失がある場合)
- 前方不注意など被害者側にも過失がある場合、過失割合に応じて減額
- 損益相殺
- 事故を原因として他から利益を受けている場合(自賠責保険金など)
6. 適正な慰謝料を獲得するための6つのポイント
適正な慰謝料を獲得するには、以下の6つのポイントを押さえておくことが重要です。
①事故後、速やかに病院を受診する
事故直後は「大したことない」と思っても、後から症状が出ることはよくあります。速やかに病院を受診することで
- 入通院慰謝料の期間が適切に確保できる
- 事故との因果関係が明確になる
- 適切な治療で早期回復が期待できる
特にむちうちなどの場合、検査で異常が見つからないこともあるため、自覚症状をしっかり医師に伝えることが大切です。
②医師の指示に従い継続して通院する
医師の指示に従って継続的に通院することで
- 入通院慰謝料が適切に計算される
- 後遺障害の認定に有利になる
- 早期の回復が期待できる
特に、むちうちの場合は週2~3回、月10日程度の通院が望ましいでしょう。 通院頻度が極端に少ないと、慰謝料が減額される可能性があります。
③適切な後遺障害等級の認定を受ける
後遺障害が残った場合、適切な等級認定を受けるには
- 被害者請求を検討する(保険会社任せにしない)
- 診断書に症状を詳細に記載してもらう
- 必要に応じて医師の意見書を添付する
後遺障害等級によって慰謝料や逸失利益が大きく変わるため、適切な等級認定を受けることが非常に重要です。
④正しい過失割合を主張する
過失割合は、慰謝料を含む全ての賠償金額に影響します。保険会社の提示する過失割合を鵜呑みにせず
- ドライブレコーダーや監視カメラの映像を確保する
- 目撃者がいれば連絡先を確保する
- 実況見分調書を入手する
- 交通事故に詳しい弁護士に相談する
⑤弁護士を立てて弁護士基準の金額を請求する
弁護士に依頼することで
- 弁護士基準での請求が可能になる
- 保険会社との交渉を専門家に任せられる
- 適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まる
- ストレスなく治療に専念できる
特に後遺障害が残ったケースや死亡事故の場合、弁護士に依頼することで賠償額が数百万円、場合によっては千万円単位で変動することもあります。
⑥保険会社の示談案をすぐに受け入れない
保険会社は初回の提示額を低めに設定することがよくあります。すぐに示談に応じず
- 提示された金額の算定基準を確認する
- 自分で慰謝料の相場を調べる
- 交通事故に詳しい弁護士に相談する
7. 慰謝料請求の流れと支払い時期
請求の流れ
- 事故発生後の対応
- 警察への通報
- 医療機関での診察・治療開始
- 保険会社への連絡
- 治療期間中
- 医師の指示に従った継続的な通院
- 症状や治療内容の記録
- 保険会社との連絡
- 症状固定後
- 後遺症が残る場合は後遺障害診断書の作成
- 後遺障害等級認定の申請
- 弁護士に相談・依頼を検討
- 示談交渉
- 保険会社と慰謝料を含む賠償金額の交渉
- 示談書の内容確認・署名
- 示談不成立の場合
- ADR(裁判外紛争解決手続)
- 調停
- 裁判
支払い時期
慰謝料を含む賠償金は、通常、示談成立から2週間程度でに支払われます。後遺障害がある場合や死亡事故の場合は、解決までに時間がかかることが多いため、事故発生から賠償金受取りまでに以下のような期間を要します。
- 軽傷で後遺障害なし:事故から半年~1年
- 後遺障害あり:事故から1年~2年
- 死亡事故:事故から1年~3年
8. 慰謝料以外に請求できる項目
人身事故では、慰謝料以外にも以下のような損害賠償を請求できます。
治療関連費用
- 治療費:病院での治療にかかった費用
- 通院交通費:通院のための交通費
- 付添看護費:入院時の付き添いや看護にかかった費用
- 器具等購入費:車椅子、コルセットなどの購入費用
- 自宅改造費:後遺障害に対応した自宅改修費用
休業損害
事故によるケガで仕事を休んだことによる収入の減少分です。
- 会社員:休業損害証明書で証明
- 自営業:確定申告書などで収入を証明
- 主婦:家事労働の代替費用として請求可能
逸失利益
後遺障害が残ったり、死亡したりしたことにより、将来得られるはずだった収入の喪失分です。
- 後遺障害逸失利益:後遺障害等級に応じた労働能力喪失率をもとに計算
- 死亡逸失利益:死亡した被害者の年収や余命をもとに計算
9. よくある質問と回答
Q1: 物損事故でも慰謝料はもらえますか?
A: 基本的に物損事故(物的損害のみの事故)では慰謝料は認められません。物が壊れた場合は、その修理費や代替品の費用で損害が補償されると考えられているためです。
例外として、特別な愛着のあるペットが死亡した場合や、特別な価値のある物が損傷した場合には、慰謝料が認められることもあります。
Q2: 物損事故から人身事故に切り替えることはできますか?
A: 可能です。事故後に痛みが出たなど、後からケガが発覚した場合は、医師の診断書を警察署に提出して人身事故に切り替えることができます。
ただし、事故発生から時間が経ちすぎると、ケガと事故の因果関係を疑われ、受理されない場合があるため、早めの対応が必要です。1週間以内の切り替えが望ましいでしょう。
Q3: むちうちで通院日数が少ないと慰謝料は減額されますか?
A: 減額される可能性があります。むちうちは画像に写りにくいケガのため、通院日数も少ないと軽いケガと判断され、慰謝料が減額されることがあります。
適切な通院頻度を保つため、主治医の指示に従い、週2~3回、月10日程度の通院が望ましいでしょう。
Q4: 人身事故の慰謝料はいつまで請求できますか?時効はありますか?
A: 慰謝料を含む損害賠償請求権には以下のような時効があります。
- 人身事故(傷害分):事故日から5年
- 人身事故(後遺障害分):症状固定日から5年
- 死亡事故:死亡日から5年
- 加害者が特定できていない事故:事故日から20年
Q5: 過失割合10対0の人身事故の場合、慰謝料はいくらになりますか?
A: 過失割合10対0の「もらい事故」の場合、被害者に全く過失がないため、過失相殺による慰謝料の減額はありません。弁護士基準で計算した場合の目安は以下のとおりです。
- 軽症(むちうちなど):19万円~89万円
- 重症:28万円~250万円
- 後遺障害あり:上記に加えて110万円~2,800万円(等級による)
- 死亡事故:2,000万円~2,800万円(立場による)
ただし、具体的な金額は、ケガの程度、通院期間、後遺障害の有無などによって大きく異なります。
まとめ
人身事故での慰謝料獲得は、知識と適切な対応が鍵となります。特に後遺障害が残る場合や重傷の場合は、弁護士に相談することで、正当な補償を受けられる可能性が高まります。この記事が、交通事故の被害に遭われた方の一助となれば幸いです。