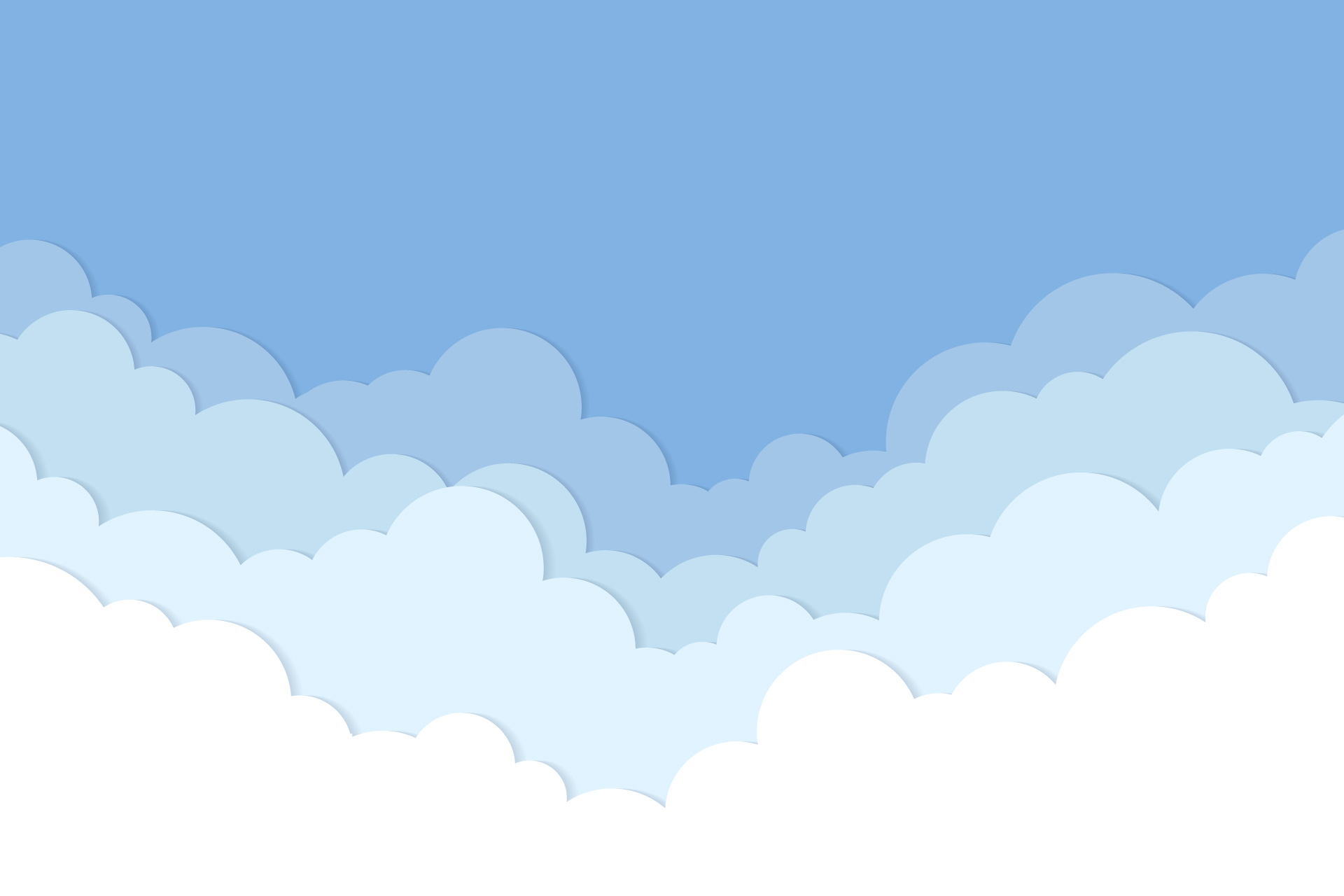もらい事故とは、被害者に全く過失がない交通事故のことをいいます。例えば、信号待ちで停車中に後ろから追突された、駐車場に停めていた車にぶつけられた、対向車がセンターラインを越えて衝突してきたなどのケースが該当します。
過失割合の観点からみると、もらい事故は「加害者対被害者=10対0」となり、被害者側に責任がないことが特徴です。
もらい事故の特徴と通常の事故との違い
示談代行サービスが使えない
もらい事故の最大の特徴は、被害者側の保険会社による「示談代行サービス」が利用できないことです。通常の事故では、相手側に対して損害賠償責任が発生する場合、自分の保険会社が示談交渉を代行してくれますが、もらい事故では被害者に過失がないため、保険会社による示談代行が法的に不可能となります。
そのため、被害者自身が加害者側の保険会社と直接交渉するか、弁護士に依頼して交渉を進める必要があります。
過失相殺がない
もらい事故では被害者に過失がないため、本来であれば過失相殺による慰謝料の減額はありません。しかし、実際の示談交渉では、加害者側が「被害者にも過失があった」と主張してくることがあるため注意が必要です。
もらい事故で請求できる慰謝料の種類
入通院慰謝料
ケガの治療のために入院・通院したことによる精神的苦痛に対する補償です。治療期間や通院頻度などにより金額が決まります。
後遺障害慰謝料
事故により後遺症が残った場合に認められる慰謝料です。後遺障害等級(1級〜14級)によって金額が変わります。
死亡慰謝料
被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料で、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料があります。
物損の場合
車両や物の破損のみの物損事故の場合は、原則として慰謝料は認められません。ただし、事故後に痛みが出てきた場合は、速やかに医療機関を受診し、人身事故として処理することが重要です。
慰謝料の算定基準と相場
慰謝料の算定には主に3つの基準があり、どの基準を適用するかで金額が大きく変わります。
自賠責基準
自賠責保険が使用する基準で、最も低額になる傾向があります。入通院慰謝料は日額4,300円を基準に計算されます。
任意保険基準
各保険会社が独自に設定する非公表の基準です。自賠責基準よりやや高い程度で、弁護士基準より低くなる傾向があります。
弁護士基準(裁判基準)
過去の裁判例をもとに弁護士や裁判所が使用する基準で、3つの中で最も高額になります。
入通院慰謝料の相場例(弁護士基準)
- むち打ちで通院3ヶ月、入院なしの場合:約53万円
- むち打ちで通院5ヶ月、入院なしの場合:約79万円
後遺障害慰謝料の相場例(弁護士基準)
- 14級(軽いむち打ち後遺症など):110万円
- 12級(重いむち打ち後遺症など):290万円
- 9級:690万円
- 5級:1,400万円
- 1級:2,800万円
同じ後遺障害でも、自賠責基準と弁護士基準では2〜3倍の差が出ることもあります。例えば、14級の後遺障害の場合、自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円と大きな差があります。
もらい事故の示談交渉で注意すべきポイント
被害者側は自身側の過失を安易に認めない
加害者側の保険会社が「被害者にも過失があった」と主張してきても、安易に認めないことが重要です。過失割合が変わると、損害賠償額が大きく減額されてしまいます。
適切な通院頻度を保つ
適正な慰謝料を受け取るためには、適切な通院頻度(概ね週2〜3回程度)を保ちながら治療することが望ましいです。通院頻度が低すぎると、怪我が軽いと判断される可能性があります。
後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を申請する
治療を続けても症状が改善しない場合は、医師に「症状固定」の診断を受け、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。
弁護士に依頼するメリット
弁護士基準での請求が可能に
弁護士に依頼することで、最も高額な弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。保険会社は被害者本人が交渉すると、任意保険基準や自賠責基準で低めの金額を提示する傾向があります。
適切な後遺障害等級認定のサポート
弁護士は後遺障害等級認定の申請をサポートし、適切な医学的所見の記載方法や補強資料の準備などをアドバイスします。これにより、症状に見合った等級を得られる可能性が高まります。
示談交渉の負担軽減
弁護士が示談交渉を代行することで、被害者は治療に専念できます。また、保険会社は弁護士が介入すると裁判になるリスクを考慮するため、交渉が有利に進むことが多いです。
弁護士費用特約の活用
自動車保険や火災保険などに「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士費用(相談料10万円、弁護士費用300万円まで)を保険でカバーできる場合があります。この特約を使っても等級や保険料に影響はありません。
よくある質問
Q: もらい事故で車が全損した場合、残ったローンの支払い分も請求できますか?
A: 車の修理代や買替費用は請求できますが、上限は事故時の車の時価額までとなります。ローン残額が時価額を超える場合、その差額分は請求できません。
Q: もらい事故で車の修理代を受け取った後、修理をしないと問題になりますか?
A: 問題ありません。車両の損傷自体が損害であり事故により生じた損害の補償であるため、実際に修理するかどうかは被害者の自由です。
Q: 加害者が死亡した場合でも損害賠償請求はできますか?
A: 加害者が死亡した場合でも損害賠償請求権は消滅しません。加害者が任意保険に加入していれば保険会社に、未加入の場合は加害者の相続人に請求することになります。
Q: 物損事故だと思っていたが、あとから痛みが出てきた場合はどうすればよいですか?
A: すぐに医療機関を受診し、診断書を取得して警察に提出することで、物損事故から人身事故への切り替えが可能です。なるべく事故から1週間以内に申請するのが望ましいでしょう。
まとめ
もらい事故では被害者に過失がないため、慰謝料を満額請求できる可能性があります。しかし、示談交渉では保険会社から適切とはいえない金額を提示されることもあるため、適切な賠償請求を行うために、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。適正な慰謝料を受け取るためには、正しい知識と適切な対応が重要です。