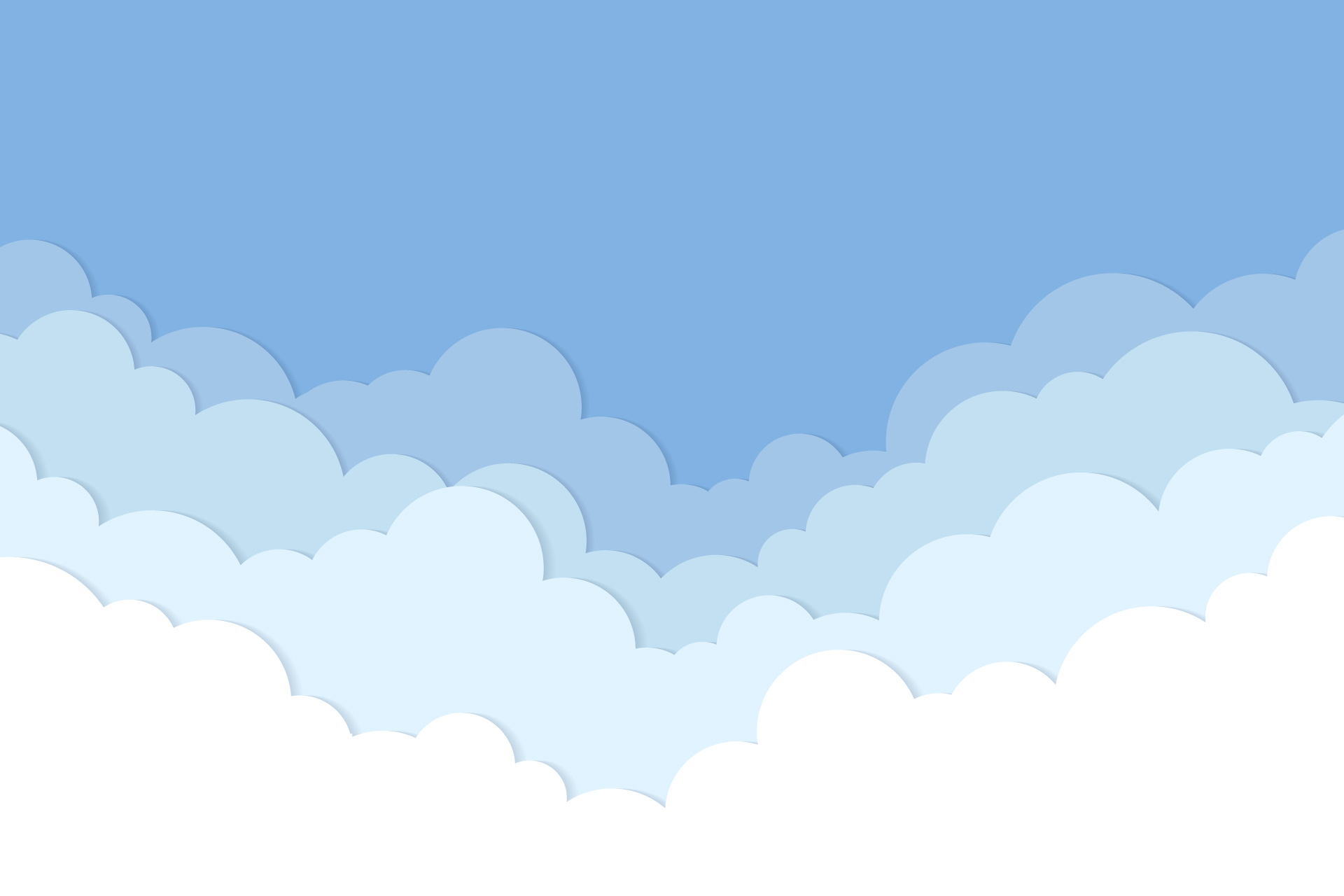逸失利益の基本概念
交通事故の結果、後遺障害が認定された場合、被害者は逸失利益を請求する権利があります。
逸失利益とは、事故がなければ将来得られたはずの収入のことを指します。具体的には以下のように分類されます。
- 死亡事案:被害者が生存していれば獲得できたであろう将来の収入全額
- 後遺障害事案:障害がない状態で得られたはずの収入と、障害を負った状態で実際に得られる収入の差額
逸失利益は、精神的苦痛に対する慰謝料とは別個の損害項目として扱われ、両者を合わせて損害賠償額が算定されます。簡潔に言えば、逸失利益は「将来にわたる休業損害」と捉えることができるでしょう。
逸失利益の算定方法(18歳以上)
18歳以上の被害者の逸失利益は、以下の公式に基づいて計算されます。
逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能期間に対応する係数
基礎収入の算定
基礎収入は通常、被害者の年間収入を基に算出されます。具体的な基準例は以下の通りです。
- 給与所得者(会社員、公務員等)
基礎収入=事故前年の源泉徴収票の金額 - 若年給与所得者(概ね30歳未満)
基礎収入=賃金センサス男女別労働者・学歴計・全年齢平均 - 事業所得者(個人企業)
基礎収入=個人企業の利益-家族等の給料等相当額
=個人企業の利益×本人寄与率 - 家事従事者(専業主婦・専業主夫など)
基礎収入=賃金センサス女子労働者・学歴計・全年齢の平均賃金
労働能力喪失率
労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級に応じて決定されます。裁判所でもこの基準が広く採用されています。
就労可能期間
通常、症状固定日から67歳までが就労可能期間とされますが、以下のような例外があります。
- 高齢者(67歳近くで症状固定):平均余命の半分を就労可能期間とする
- 特定の症状(例:むち打ち):5年や10年など、固定期間が設定されてしまう場合が多いです。
注意:将来の収入を現在価値に換算するため、ライプニッツ係数を使用します。
18歳未満の被害者の逸失利益算定
18歳未満の未就労者の逸失利益は、以下の方法で計算されます。
逸失利益 = 平均賃金 × 労働能力喪失率 × (67歳までの係数 – 18歳までの係数)
- 基礎収入には賃金センサスの平均賃金を使用
- 就労期間は18歳から67歳までの49年間を想定
- ライプニッツ係数は、(症状固定時から67歳) – (症状固定時から18歳) で算出
逸失利益が認められないケースと対策
逸失利益の請求が認められない主な理由と、それに対する対応策を解説します。
1. 後遺障害等級未認定
後遺障害等級の認定は逸失利益請求の前提条件です。以下の手順を踏むことが重要です。
- 担当医に後遺障害診断書の作成を依頼
- 後遺障害等級認定の申請手続きを行う
注意:整骨院のみの通院歴では、医師による診断書作成が困難な場合があります。定期的な病院受診が必要です。
2. 無収入状態
失業中や無収入でも、以下の状況では逸失利益が認められる可能性があります。
- 就労能力と意欲があり、近い将来の就職可能性が高い場合
- 学生の場合、将来の予想収入を基に算定
- 専業主婦(夫)の場合、家事労働の経済的価値を評価
保険会社が支払いを拒否した場合は、交通事故専門の弁護士に相談し、法的観点からの評価を受けることをお勧めします。
3. 減収なし
後遺障害があっても実際の収入減がない場合でも、以下のような状況では逸失利益が認められることがあります。
- 将来的なキャリアへの悪影響が予想される
- 業務遂行に以前より多くの時間や労力を要する
- 後遺障害により従来の業務遂行に支障がある
年金生活者などでも、具体的な生活上の支障を立証できれば、逸失利益が認められる可能性があります。
4. 労働能力低下なし
外見上の障害や特定の骨折後遺症など、労働能力への影響が不明確な場合があります。このような場合。
- 醜状障害による社会生活上の支障
- 骨折後遺症による日常生活や仕事への具体的影響
これらの影響を具体的に説明し、立証することが重要です。
逸失利益をもらえるようにするためにすべきこととは
1. 適切な後遺障害等級の取得
後遺障害等級認定には2つの方法があります。
- 事前認定:保険会社主導の手続き
- 被害者請求:被害者自身による申請
被害者請求の場合、弁護士に相談し、十分な証拠を準備することが重要です。また、後遺障害診断書作成時には、弁護士のアドバイスを受けながら医師と相談することをお勧めします。
2. 後遺障害の影響を明確化
後遺障害による具体的な支障を明らかにすることが重要です。特に仕事にどのような影響が生じてるのかを明らかにすべきです。
- 痛みによる業務効率低下や集中力減退
- 外見の変化による職場での不利益
これらの実態を詳細に記した陳述書を提出することで、適切な等級認定や有利な示談交渉につながる可能性が高まります。
3. 交通事故に強い専門家への相談
保険会社の対応に疑問を感じた場合は、交通事故に精通した弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼することで得られる利点は
- 法的基準や判例に基づく専門的アドバイス
- 裁判基準に基づく適正な賠償額の請求
- 必要書類の作成や証拠収集のサポート
- 保険会社との交渉代行
などがあげられます。