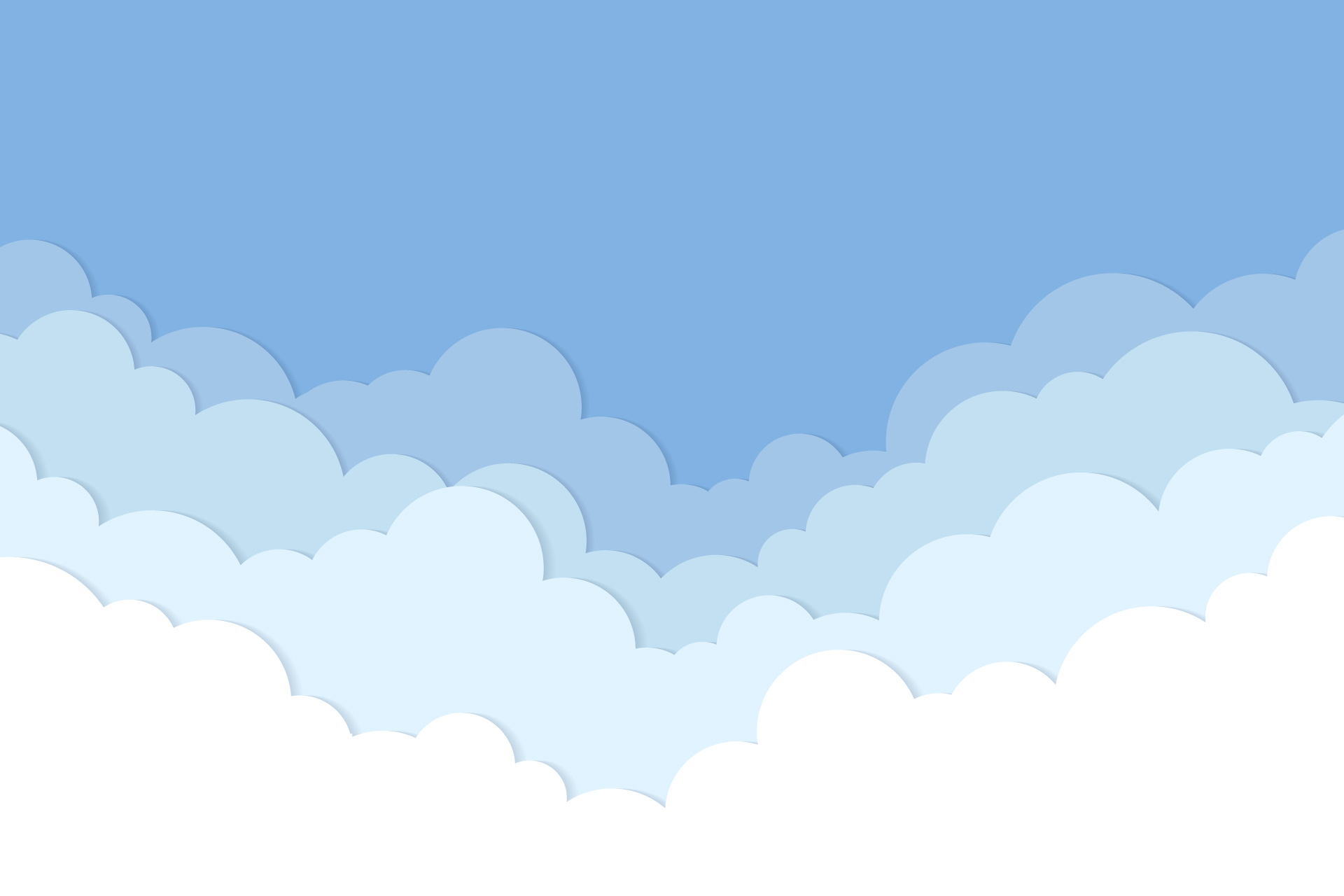本記事では、後遺障害認定を適切に受けるための重要ポイントをお伝えいたします。あわせて弁護士を活用する意義についてもお伝えいたします。
1. 後遺障害診断書の綿密な作成
後遺障害認定において、診断書は審査の根幹を成す不可欠な文書です。審査は診断書に記載された情報のみに大きく依拠して行われるため、症状の詳細な記録が極めて重要です。
- •ジャクソンテストやスパーリングテスト等の神経学的検査結果
- 関節可動域の詳細な検査結果
- 疼痛箇所の正確な位置情報
- 外見上の変化(醜状障害)の正確な大きさも示した具体的描写
これらの情報が欠落すると、該当症状が審査対象から除外される恐れがあります(なお、大前提として自覚症状の記載が漏れると審査の俎上に載りません)。診断書の内容を被害者自身で精査するか、専門弁護士の助言を仰ぐことを強く推奨します。
2. 医療専門家の指示に基づく継続的な治療
後遺障害等級の中で最多の認定を受けるのは14級9号です。この等級は、医学的に説明可能な持続的な神経症状が認められる場合に適用されます。
認定の重要な判断基準の一つに治療期間がありますので、個人の判断で治療を中断することは望ましくありません。
保険会社が早期の治療終了を提案してきても、症状が残存し医師が継続治療を推奨する場合は、治療の継続を検討すべきです。保険会社の提案を鵜呑みにせず、専門弁護士に相談の上、今後の方針を決定することが賢明です。
3. 不適切な認定結果に対する異議申立て
後遺障害認定結果が不適当と判断される場合、異議申立ての実施を検討すべきです。この手続きは、時効の範囲内であれば複数回行うことが可能です。
しかし、同様の主張や証拠の再提出のみでは等級の変更は期待できません。認定理由を詳細に分析し、新たな証拠を収集することが重要です。
- 主治医との詳細な面談
- 医療照会書の取得
- 画像診断の専門的解析
- 詳細な医療記録の入手
これらの新規証拠を基に再度異議申立てを行うことで、より適切な等級認定の可能性が高まります。
4. 交通事故専門弁護士の活用
後遺障害に精通した弁護士に相談・依頼することで、適切な等級認定の可能性が大幅に向上します。弁護士の専門知識と経験は、以下の点で特に有効です:
認定見込みの的確な予測
専門弁護士は、症状に基づいて認定される可能性が高い等級を予測できます。これにより、不当に低い等級を受け入れることや、不必要な異議申立てを避けることが可能になります。
診断書の徹底的な検証
弁護士による診断書のチェックは、重要な症状の記載漏れを防ぎ、審査対象となる情報を最大化します。
申請手続きの最適化
後遺障害申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。弁護士は通常、認定に有利な追加資料(事故状況の写真、医療記録、専門家の意見書など)を積極的に提出します。
賠償額の最大化
弁護士の介入により、最も高額な弁護士基準(裁判基準)での解決が期待できます。特に後遺障害が認定された場合、慰謝料や逸失利益などの項目で大幅な増額が見込めます。
弁護士費用特約の有効活用
多くの保険契約に含まれる弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用の負担を軽減できます。この特約は使用しても保険料に影響せず、適用範囲も広いため、積極的な活用が推奨されます。ただし、追加費用が必要な場合もあるため、事前の確認が重要です。
後遺障害認定は被害者の将来に大きな影響を与える重要な手続きです。適切な認定を受けるためには、専門的知識と経験が不可欠です。交通事故専門の弁護士に相談することで、公正な賠償を受ける可能性を最大化し、被害者の権利を適切に守ることができます。
後遺障害の等級
後遺障害に関しては、その症状の重篤さに応じて1級から14級までの等級が分かれており、等級が認定された場合には、
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益等、それぞれの等級に対応した補償が支払われる仕組みとなっています。
後遺障害の等級については、自動車損害賠償保障法施行令別表に定められています。
1. 介護を要する場合
| 等級 | 介護を要する後遺障害等級 | 労働能力 喪失率 |
| 第1級 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% |
| 第2級 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 100% |
スクロールできます
2. 介護を要しない場合
| 等級 | 介護を要する後遺障害等級 | 労働能力 喪失率 |
| 第1級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 四 両上肢の用を全廃したもの 五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
| 第2級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 両上肢を手関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの | 100% |
| 第3級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの | 100% |
| 第4級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | 92% |
| 第5級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの | 79% |
| 第6級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの | 67% |
| 第7級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失つたもの | 56% |
| 第8級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの | 45% |
| 第9級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの | 35% |
| 第10級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 27% |
| 第11級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 20% |
| 第12級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手のこ指を失つたもの 十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの | 14% |
| 第13級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 六 一手のこ指の用を廃したもの 七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 9% |
| 第14級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの | 5% |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。