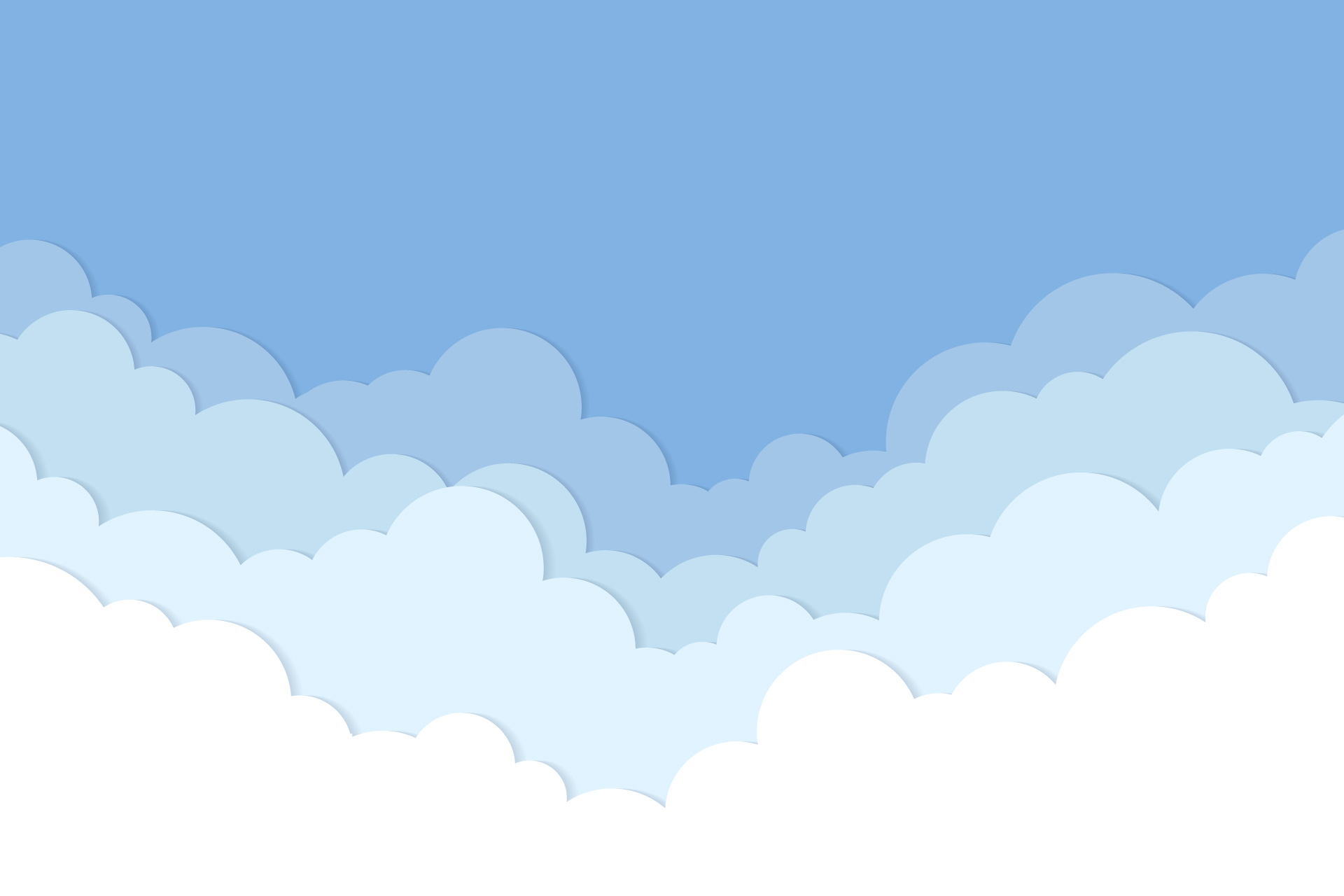本記事では、後遺障害認定において不可欠な診断書についてお伝えいたします。
後遺障害の診断書について
後遺障害診断書は、後遺障害認定手続において不可欠な書類です。この手続きでは、診断書などに基づいて後遺障害等級が決定され、さらにその等級によって損害賠償額が大きく左右されます。
以下では、後遺障害診断書の重要性と作成のポイントについて詳しく説明いたします。
症状固定から後遺障害診断書の作成まで
治療を継続しても効果が期待できなくなった状態を「症状固定」といいます。症状固定時に残存している症状は、後遺障害として認定を受ける必要がありますが、症状は目に見えないため、そのままでは認定されません。
後遺障害として認定を受けるためには、以下の手順が必要です。
- 主治医による症状の診断: 症状の有無や程度を詳細に診断します。
- 診断書の作成: 主治医が診断結果に基づいて診断書を作成します。
- 損害保険料率算出機構への提出: 作成された診断書を後遺障害を認定する機関である損害保険料率算出機構に提出します。
この主治医が作成する後遺障害に関する診断書を後遺障害診断書と呼びます。
後遺障害診断書作成におけるポイントとは?
後遺障害(後遺症)の認定審査は、審査機関があなたと直接面談して判断するわけではありません。審査は、主治医が作成した後遺障害診断書をもとに行われる書面審査です。
実態がどうであれ、「書面」で判断されてしまうということです。
すなわち、後遺障害診断書の内容が認定結果に大きな影響を与えるのです。
しかし、全ての医者が適切な後遺障害診断書を作成するノウハウを持っているとは限りません。あなたの症状を正確かつ詳細に後遺障害診断書に記載してもらうことが、後遺障害(後遺症)の認定を受けるための鍵となります。
症状が固定したら、主治医に後遺障害診断書を書いてもらいます。交通事故の損害賠償請求に使用する後遺障害診断書は、通常、定型の書式を使用します。後遺障害(後遺症)の内容により、複数の書式があり、検査結果を記載するための特別な書式も存在します。
【後遺障害診断書を作成してもらうためのポイント】
- 全ての必要な検査を受ける: 症状を客観的に評価するために必要な検査は漏れなく受けましょう。これには血液検査、画像診断(X線、MRI、CTなど)、神経学的検査などが含まれる場合があります。
- 可動域(関節が動く範囲)を正確に測定: 特に整形外科的な障害の場合、関節の可動域は重要な指標となります。医師に正確な測定を依頼し、その結果を診断書に明記してもらいましょう。
- 空欄をなくす: 診断書の空欄は「正常」と判断される可能性があります。全ての項目に記入があるよう、医師に確認しましょう。
- 他覚所見と自覚症状を詳細に記載: 医師が客観的に確認できる症状(他覚所見)と、あなたが感じている症状(自覚症状)の両方を詳しく記載してもらいましょう。痛みの程度、頻度、日常生活への影響なども含めます。
- 症状のある部位を具体的に示す: 「腰が痛い」ではなく、「第4腰椎周辺に持続的な痛みがある」というように、具体的な部位を明記してもらいましょう。
- 画像所見の詳細な記載: X線やMRIなどの画像診断結果がある場合、画像の種類と撮影日を記載し、その画像から読み取れる症状を正確かつ詳細に記載してもらいましょう。
- 事故とケガ、症状の関連性を明確に: 事故で負ったケガと、現在残っている症状との因果関係を具体的に説明してもらいましょう。これは、症状が事故に起因することを示す重要な証拠となります。
- 画像所見と症状の関連性を明確に: 画像で確認できる異常所見と、実際に残っている症状がどのように関連しているかを具体的に記載してもらいましょう。これにより、症状の客観性が高まります。
これらのポイントに注意して後遺障害診断書を作成してもらうことで、より正確で詳細な診断書となり、適切な後遺障害認定につながる可能性が高まります。