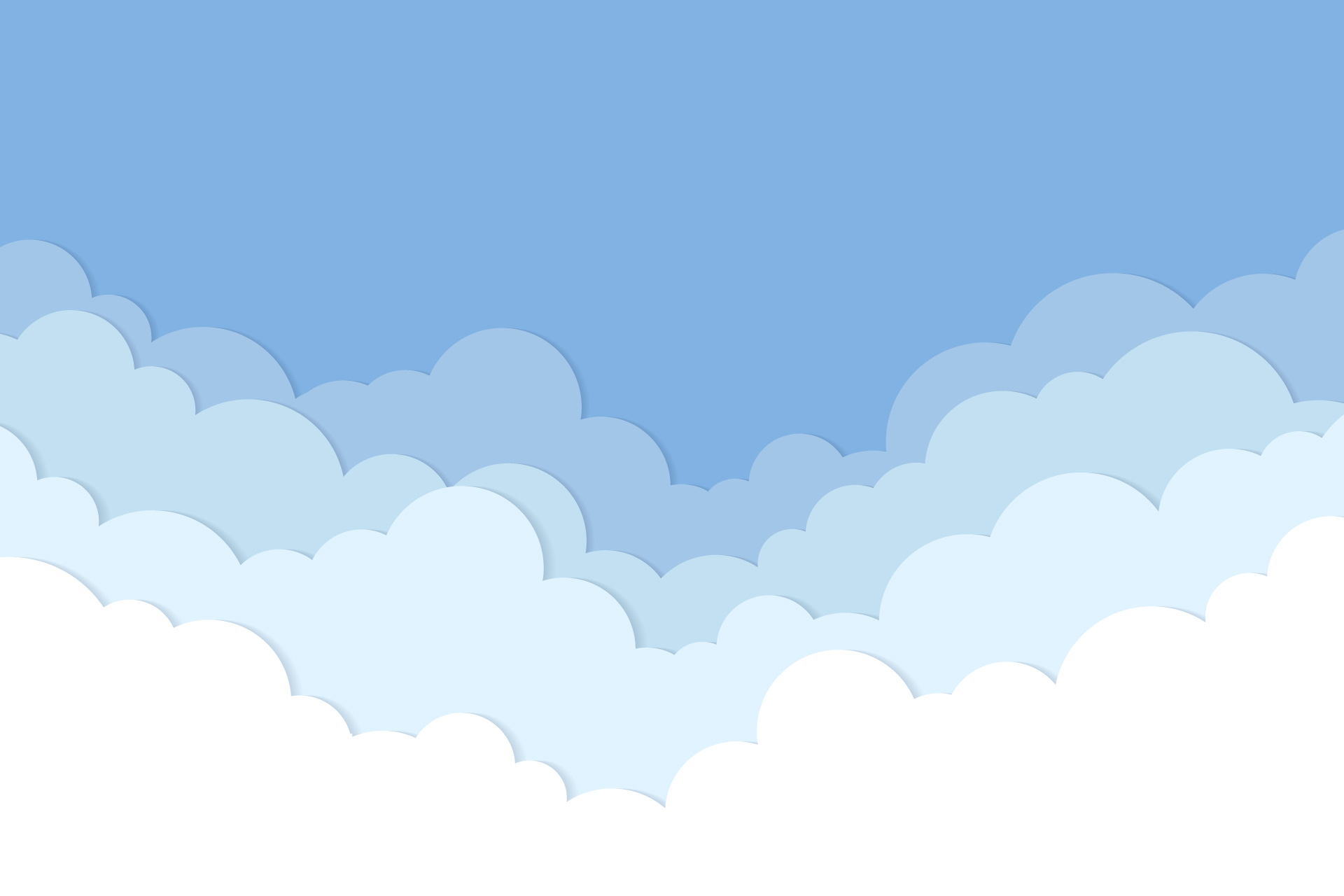交通事故に遭われた場合、精神的・身体的な苦痛に対する補償として「慰謝料」を請求することができます。しかし、適正な慰謝料を受け取るためには、慰謝料の計算方法や基準を正しく理解しておく必要があります。この記事では、交通事故の慰謝料とは何か、どのように計算されるのか、適正な慰謝料を受け取るためのポイントについて解説します。
交通事故の慰謝料とは
慰謝料とは、交通事故による精神的・身体的な苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。物的損害とは異なり、精神的苦痛という目に見えない損害に対する補償であるため、その金額は各種基準や判例をもとに算定されます。
交通事故の慰謝料は主に以下の3種類に分けられます。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料):交通事故によるケガの治療のために入院・通院したことに対する慰謝料
- 後遺障害慰謝料:交通事故により後遺症が残った場合に支払われる慰謝料
- 死亡慰謝料:被害者が事故により死亡した場合に支払われる慰謝料
慰謝料の3つの計算基準
交通事故の慰謝料を計算する基準は主に3つあります:
1. 自賠責保険基準
国が定める最低限の補償基準です。自動車損害賠償保障法に基づいて設定されており、自賠責保険から支払われる慰謝料はこの基準で計算されます。金額は3つの基準の中で最も低くなりがちです。
2. 任意保険基準
各保険会社が独自に設定している基準です。保険会社によって異なり、一般的には自賠責基準より高く、弁護士基準より低い金額となります。加害者側の任意保険会社が示談交渉の際に提示してくる金額は、この基準に基づいていることがほとんどです。
3. 弁護士基準(裁判基準)
裁判所の判例をもとに作られた基準で、「赤い本」とも呼ばれる基準です。3つの基準の中で最も高額になることが多く、弁護士が示談交渉や訴訟を行う際にはこの基準が用いられます。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、ケガの程度や入通院期間によって算定されます。
自賠責保険基準による計算
自賠責保険基準では、以下の計算式で入通院慰謝料を算出します:
- 対象日数 × 4,300円(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)
対象日数は以下のいずれか少ない方を採用します:
- 入通院期間(事故日から治療終了日または症状固定日までの期間)
- 実治療日数(入院日数+実通院日数×2)
計算例: 通院期間6ヶ月(180日)、実通院日数80日、入院なしの場合
- 通院期間:180日
- 実通院日数の2倍:80日×2=160日
160日<180日なので対象日数は160日となり、 4,300円×160日=688,000円が自賠責基準での入通院慰謝料となります。
弁護士基準による計算
弁護士基準では、入院期間と通院期間に応じた算定表を用いて慰謝料を算出します。ケガの種類によって2種類の表が使い分けられます:
- 表Ⅰ(通常のケガの場合):骨折、脱臼、他覚的所見のあるむちうちなど
- 表Ⅱ(軽いケガの場合):軽い打撲や捻挫、他覚的所見のないむちうちなど
計算例: 骨折で通院6ヶ月、入院なしの場合、表Ⅰによると約116万円となります。 他覚的所見のないむちうちで通院6ヶ月、入院なしの場合、表Ⅱによると約89万円となります。
同じ通院期間でも、ケガの程度や種類によって慰謝料の金額は大きく異なります。また、同じケースでも自賠責基準では68.8万円、弁護士基準では116万円というように、基準によって金額に差が生じることが分かります。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級(1級〜14級)に応じて金額が決まります。
自賠責保険基準と弁護士基準の比較
後遺障害慰謝料の金額は、等級ごとに以下のように定められています:
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
| 1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
| 2級 | 998万円 | 2,370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1,990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1,670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1,400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1,180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1,000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害等級の認定を受けるためには、症状固定後に医師の診断書をもとに申請手続きを行う必要があります。適切な等級認定を受けることが、適正な慰謝料を受け取るための重要なポイントです。
死亡慰謝料の計算方法の例
死亡慰謝料は、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料に分けられます。
自賠責保険基準による計算
自賠責保険基準では、以下のように計算されます:
- 被害者本人の慰謝料:400万円
- 遺族の慰謝料:
- 遺族1人の場合:550万円
- 遺族2人の場合:650万円
- 遺族3人以上の場合:750万円
- 被扶養者がいる場合は上記に200万円を加算
計算例: 被害者に配偶者と子供がいる場合 400万円(被害者本人)+ 650万円(遺族2人)+ 200万円(被扶養者あり)= 1,250万円
弁護士基準による計算
弁護士基準では、被害者の家庭における立場によって金額が異なります:
- 一家の支柱だった場合:2,800万円
- 配偶者・母親だった場合:2,500万円
- その他の場合:2,000万円〜2,500万円
弁護士基準の金額には、遺族の慰謝料も含まれています。
適正な慰謝料を受け取るためのポイント
1. 早期に医療機関を受診する
事故直後から適切な医療機関で診察を受け、定期的に通院することが重要です。通院記録は慰謝料算定の重要な根拠となります。
2. 自覚症状をしっかり伝える
痛みやしびれなどの症状を医師に詳しく伝え、カルテに記録してもらいましょう。後遺障害の認定や慰謝料の算定に影響します。
3. 治療は医師の指示に従って継続する
保険会社から「そろそろ治療を終了しては」と提案されても、医師が治療継続が必要と判断する場合は、治療を続けることが大切です。
4. 後遺障害の認定申請を適切に行う
症状固定後、後遺症が残る場合は後遺障害の認定申請を行いましょう。専門医による適切な診断書の作成が重要です。
5. 弁護士に相談する
慰謝料の交渉は専門知識が必要です。弁護士に依頼することで、弁護士基準での慰謝料増額交渉が可能となります。弁護士費用特約が付いている場合は、費用負担を気にせずに相談できます。
弁護士に依頼するメリット
- 適正な賠償金額の獲得:弁護士基準での慰謝料請求が可能になり、一般的に自賠責基準や任意保険基準より高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
- 専門的な交渉力:保険会社との交渉は専門知識が必要です。弁護士は交通事故の賠償について専門的な知識を持ち、適切な交渉を行うことができます。
- 精神的負担の軽減:被害者は治療に専念でき、複雑な交渉や手続きを弁護士に任せることができます。
- 弁護士費用特約の活用:ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用を保険でカバーできます。
まとめ
交通事故の慰謝料は、その計算基準によって金額が大きく異なります。加害者側の保険会社が提示する金額は、通常、自賠責基準や任意保険基準に基づいており、適正な金額より低いことが多いです。適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準での計算が望ましく、そのためには弁護士への相談が効果的です。
交通事故に遭われた場合は、早めに専門家に相談し、適切な対応を取ることで、正当な補償を受けられるよう心がけましょう。当事務所では交通事故の無料相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。