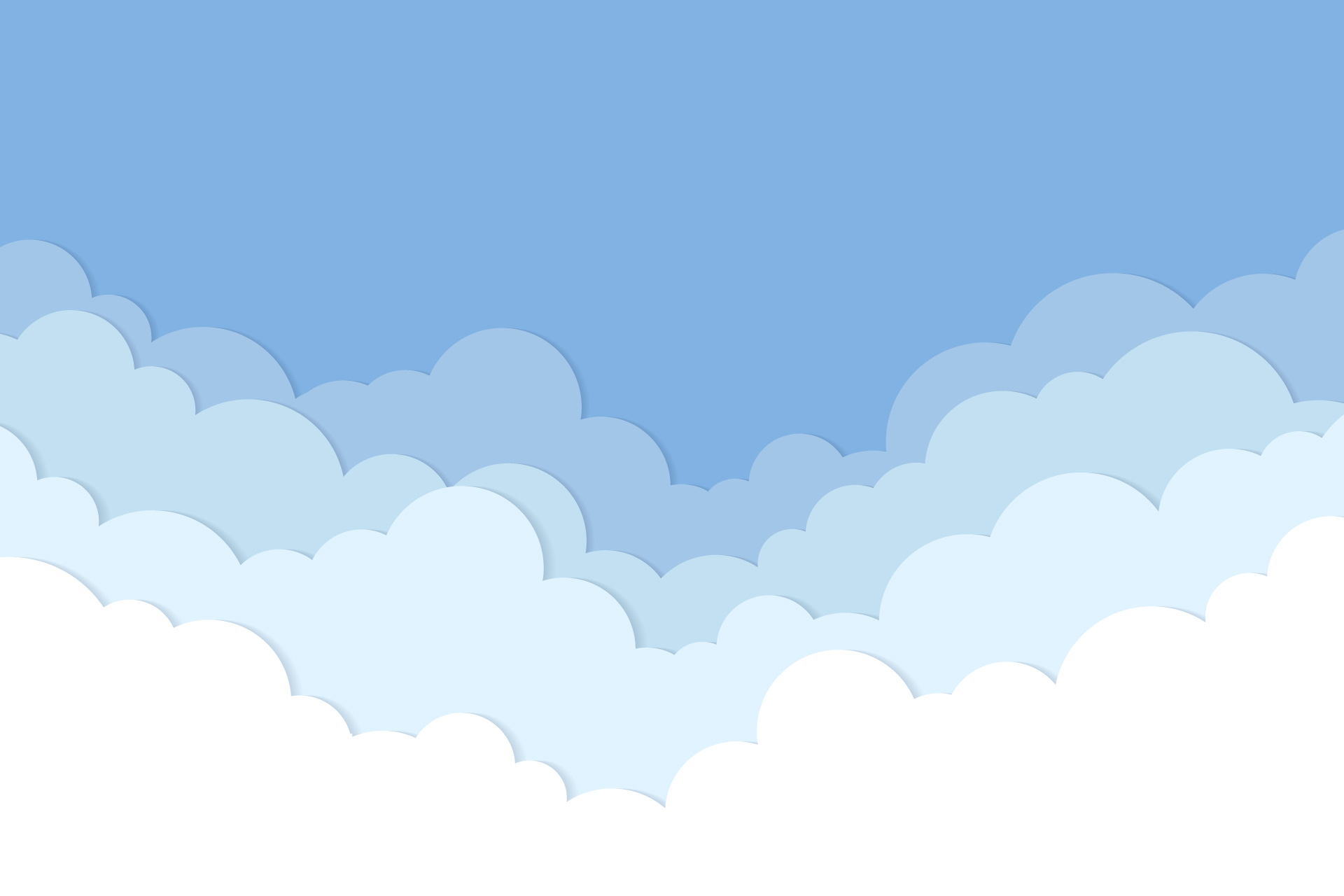交通事故に遭ってしまうと、怪我の治療や日常生活の立て直しに追われる中、保険会社からの示談の提案に対応しなければならないこともあります。事故の混乱の中で、「早く終わらせたい」という気持ちから安易に示談に応じてしまうと、後になって「もっと賠償金をもらえたはずだった」と後悔することもあるかもしれません。
この記事では、交通事故の被害者が知っておくべき示談交渉のポイントを、できるだけわかりやすく解説します。適切な示談交渉を行うことで、あなたが本来受け取るべき賠償金をしっかり受け取れるよう、参考にしていただければ幸いです。
示談って何だろう?
「示談」というと難しく感じるかもしれませんが、簡単に言えば当事者同士の話し合いで紛争を解決する方法です。
交通事故の場合、被害者と加害者(実際には加害者側の保険会社が窓口になることがほとんどです。)との間で、「過失割合はどうするか」「賠償金はいくら支払うか」といったことを決め、それを示談書という書面にまとめて取り交わします。
この示談書に署名・押印すると法的に拘束力を持ち、原則として後から「やっぱりもっと欲しい」と言っても原則的に認められません。だからこそ、示談書の内容をしっかり確認して、納得した上で合意することが大切です。
例えば、交通事故で腰を痛めたものの、保険会社から「これ以上治療を続けても改善は見込めないでしょう」と言われて示談を急かされ、50万円の賠償額で示談に応じたとしましょう。
しかし、その後症状が悪化して長期間の治療が必要になったり、休業も余儀なくされたりした場合、一度示談が成立しているため追加の賠償は受けられなくなりかねません。
こうした事態を避けるためにも、示談の仕組みと注意点を知っておく必要があります。
いつ示談交渉を始めるべき?
示談交渉のタイミングは非常に重要です。保険会社は早期解決を望むあまり、「そろそろ示談にしませんか?」と持ちかけてくることも少なくありません。しかし、被害者にとって最適なタイミングは状況によって異なります。
怪我だけの場合
怪我が完全に治った(完治した)と医師に診断された後が適切です。治療中に示談を結んでしまうと、後から治療が長引いたり、想定外の治療が必要になったりしても、追加の賠償を求めることができなくなります。
例えば、むち打ちなどの頚部捻挫は、一時的に症状が軽くなっても、後から痛みが強くなることがあります。治療途中で示談に応じると、後で症状が悪化しても保険会社からは「もう示談は済んでいます」と言われてしまうおそれがあります。
後遺障害が残りそうな場合
医師から「症状固定」の診断を受け、さらに後遺障害等級の認定を受けた後が適切です。症状固定とは、治療を続けても症状がそれ以上よくならない状態に達した時点をいいます。
実際にあった事例では、交通事故で指の骨折と神経損傷を負った女性が、治療を3か月ほど続けた時点で保険会社から「もう治療は十分でしょう」と示談を勧められました。しかし、弁護士に相談したところ、症状固定の診断を受けてから後遺障害の申請をするようアドバイスされ、結果的に12級の認定を受け、当初提示されていた金額の3倍以上の賠償金を受け取ることができました。
保険会社からの「そろそろ症状固定でしょう」という言葉をうのみにせず、必ず主治医の判断を仰ぎましょう。症状固定は医師が判断することであり、保険会社が決めることではありません。
示談金はどう計算される?
「適正な賠償金はいくらなのか?」これは多くの被害者が抱く疑問です。実は、賠償金の計算方法には主に3つの基準があり、どの基準を使うかで金額が大きく変わってきます。
- 自賠責基準 – 最低限の補償を目的とした基準で、金額は一番低めです
- 任意保険基準 – 各保険会社が独自に定める基準で、自賠責より高めですが、裁判所基準より低めです
- 裁判所(弁護士)基準 – 過去の裁判例をもとにした基準で、一般的に最も高額になります
例えば、同じ12週間の通院でも、いずれの基準を使うかによって大きな差が出ることがあります。
保険会社は当然、自社の支払いを抑えるために自賠責基準や任意保険基準で示談金を計算します。「これが精一杯の金額です」と言われても、それは保険会社の立場からの「精一杯」であり、被害者が本来受け取るべき適正な金額とは限りません。
特に、弁護士が介入すると賠償金が増額するケースは少なくありません。例えば、弁護士が介入する前は約80万円の賠償案だったものが、交渉の結果150万円以上に増額したことがあります。
示談書に記載される主な項目
示談書は法的な契約書ですので、何が書かれているのかをきちんと理解することが重要です。主な項目を見ていきましょう。
1. 事故の表示
事故の日時や場所、当事者(被害者・加害者)の情報などが記載されます。これは「どの事故についての示談なのか」を明確にするためのものです。記載内容に間違いがないか確認しましょう。
2. 示談内容
事故の責任の割合(過失割合)や、支払われる賠償金の総額、支払い方法などが記載されます。ここでは特に過失割合と賠償金額をしっかり確認することが大切です。
過失割合は、「被害者側にも〇%の過失がある」というもので、この割合に応じて賠償金が減額されます。例えば、本来100万円の賠償金が認められるケースでも、被害者に30%の過失があれば、実際の賠償金は70万円になります。保険会社から提示される過失割合が妥当かどうか、よく検討する必要があります。
3. 清算条項
「この示談で全ての債権債務関係を清算し、今後一切の請求をしない」といった内容が記載されます。これがあると、後から症状が悪化しても追加の賠償請求ができなくなるので要注意です。
後遺症の可能性がある場合は、「後遺障害が認められた場合には、別途協議する」という留保条項を入れてもらうよう交渉しましょう。保険会社はこの留保条項を入れたがらないことが多いですが、被害者の権利を守るためには重要な条項です。
4. 違約条項
賠償金が約束通り支払われなかった場合の取り決めです。保険会社が相手なら支払いの遅れの心配は大きくありませんが、加害者個人が支払う場合には特に重要になります。
5. 当事者の署名・押印
示談内容に合意した証として、最後に署名と押印をします。この署名・押印は示談が成立したことを示すものですから、内容に納得がいかない部分があれば、署名・押印する前に解決しておく必要があります。
示談交渉での心構えと注意点
焦らず冷静に対応する
保険会社の担当者は交渉のプロです。「早く解決しましょう」「これが限界の金額です」などと言われても、焦らずに冷静に判断することが大切です。
例えば、保険会社から「今なら特別に上乗せして90万円にします」と言われ、期限を切られたことで焦って示談に応じてしまったとしましょう。しかし後から調べると、同様の怪我なら120万円以上が相場だったことがわかることもあります。
保険会社の「今だけ」「特別に」という言葉に惑わされないようにしましょう。
物的損害と人身損害の示談の関係
交通事故では、車の修理費などの「物的損害」と、怪我の治療費や慰謝料などの「人身損害」があります。多くの場合、物損の示談が先に進められますが、ここで合意した過失割合が後の人身損害の示談にも適用されることが多いです。
例えば、車両の衝突角度などから被害者に20%の過失があると合意してしまうと、後の怪我の治療費などの賠償も20%減額されてしまうこともあります。物損の示談であっても、過失割合については慎重に判断する必要があります。
示談金の内訳を確認する
示談書には賠償金の総額だけが記載されることが多いので、その内訳を別途書面で確認しましょう。治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料など、項目ごとの金額が適切かどうか確認することが重要です。
特に休業損害(事故のために仕事を休んで減った収入の補償)や慰謝料の計算は複雑なので、保険会社の計算が適切かどうか確認するのは難しいかもしれません。不安な場合は弁護士に相談することをお勧めします。
時効に注意する
交通事故の損害賠償請求権には時効があります。人身損害の場合、時効は損害及び加害者を知った時から5年です。したがって、一般的には事故発生日から5年で時効となり、また後遺障害がある場合は、症状固定日から5年で時効となります。物的損害とは時効期間が異なる点にも注意が必要です。
「保険会社とずっと交渉していたのに、いつの間にか時効になっていた」ということがないよう、時効が迫っている場合は「時効の更新」のための手続きを行うか、早めに示談を成立させる必要があります。
弁護士に相談するメリット
「弁護士に相談するのはハードルが高い」と思う方も多いかもしれませんが、交通事故の被害者にとって、弁護士への相談は大きなメリットがあります。
示談金の増額が期待できる
前述の通り、賠償金の計算基準には3種類あり、弁護士が介入すると裁判所基準での計算が可能になります。実際に、弁護士介入前と後で賠償金が倍近くになるケースも珍しくありません。
後遺障害等級の適切な認定をサポート
後遺障害の等級認定は、賠償金額に大きく影響します。例えば、同じ首の痛みでも、9級と認定されれば約690万円、12級だと約290万円、14級だと約120万円と、等級によって大きな差があります。弁護士は適切な等級認定のための申請書類作成や手続きをサポートします。
保険会社主導の「事前認定」ではなく、被害者自身が申請する「被害者請求」の方が有利な認定を受けられることが多いのですが、この手続きは複雑です。弁護士に依頼すれば、この手続きを代行してもらえます。
示談書の内容チェック
示談書には専門的な法律用語が使われていることも多く、一般の方には理解しづらい部分もあります。弁護士は示談書の内容をチェックし、不利な条件や見落としがないか確認してくれます。
弁護士費用特約を活用できる
「弁護士に依頼すると費用がかかる」と心配する方も多いですが、実は自動車保険やバイク保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、基本的に自己負担なしで弁護士に依頼することができる場合があります。自分の保険だけでなく、家族の保険にこの特約が付帯していれば利用できる場合もあるので、確認してみる価値はあります。
まとめ
交通事故の示談交渉は、被害者にとって人生で何度も経験するものではありません。一方、保険会社にとってはある面においては日常的に発生する業務であり、示談交渉のプロと言えます。このような経験の差や被害者側の知識不足が、不利な示談結果につながることも少なくありません。
示談書に署名する前に、内容をしっかり理解し、不明点や不安があれば遠慮なく質問しましょう。納得のいかない条件であれば、安易に合意する必要はありません。
特に清算条項や過失割合については慎重に確認することが大切です。
もし示談交渉でお悩みであれば、一人で抱え込まず、弁護士に相談することをお勧めします。